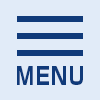

前号で書きましたことの繰り返しになりますが、連結財務諸表作成の流れはおおよそ次のようになります。
(1)個別財務諸表と連結用資料の作成
(2)連結子会社作成資料のチェック
(3)連結ソフトへの連結会社財務諸表等の入力
(4)開始仕訳の作成・入力
(5)資本連結仕訳の作成・入力
子会社の資産・負債の時価評価、投資と資本の消去
(5)連結仕訳の作成・入力
取引高の消去、債権債務の消去、債権債務の消去に伴う貸倒引当金の調整、未実現損益の消去、税効果会計の適用など
(6)組替仕訳の作成・入力
(7)連結財務諸表の作成
前号ではこうした一連の作成プロセスの中で特長的な修正仕訳と開始仕訳について述べました。
今回は上記の(1)のプロセスについて少し関連する事項をふまえながら説明してきたいと思います。
まずは、連結会社(親会社、連結子会社、持分法適用会社)が個別のそれぞれの財務諸表を作成するところから始まります。
そして、個別財務諸表と共に連結財務諸表作成の基礎資料も作成します。
この作成資料は連結パッケージといわれることが多く、ここでもその言葉を使っていきます。
パッケージといいますとソフトウエアをイメージしやすいですが、多くの基礎資料が集められた一連の書類という意味で「パッケージ」という言葉が使われていると思われます。
連結パッケージには連結修正仕訳を起こすための資料や、連結財務諸表の注記をするための各連結会社の資料、その他が含まれています。
連結修正仕訳を起こすための資料とは、もう推測がつくかもしれませんが、
(1)連結会社間の取引高や債権債務
(2)連結会社からの購入した固定資産・連結会社に売却した固定資産の明細
(3)連結会社が保有する他の連結会社株式明細
などがあり、
連結財務諸表の注記をするための資料とは
(1)リース契約にかかる資料
(2)関連当事者との取引の資料
(3)税効果会計の適用に関する資料
(4)保有有価証券の区分
(5)その他の資料
などがあります。
また、その他の資料としては連結会社のその他の勘定科目、すなわち、その他流動資産・負債、その他固定資産・負債、雑収入ならびに雑損失などのうち、例えば100万円以上の項目を記載する資料も含まれます。
これはどういう意味かといいますと、連結会社の規模はそれぞれ違いますので親会社では独立した勘定科目で表示されているが、子会社では金額がわずかなために「その他」で表示している場合があります。
具体例をあげますと、親会社では固定資産除却損を損益計算書で計上しているが、子会社では「その他の特別損失」などと表示している場合です。
こうした場合、子会社の固定資産除却損を親会社のそれと合計して連結損益計算書に計上しないと正しい金額を表示できなくなってしまうという問題が発生してしまいます。
このように親会社から見れば子会社のその他の科目に何が隠れているかわからないと正しい金額を財務諸表に計上できないため、ある金額以上の「その他」の金額についてはリストアップしてもらうようにしているはずです。
こうして連結パッケージが作成されて親会社に送付されます。連結パッケージの紙媒体の場合もあるでしょうし、EXCELファイルなどの電子媒体の場合もあります。
これまで説明してきましたように、連結財務諸表を作成するために連結子会社の個別財務諸表を集計し、合算します。
このときに個別財務諸表について次のような問題があります。
(1)連結子会社Aの決算期が親会社と異なるとき、単純にA社の直近財務諸表を合算していいのか。
(2)連結子会社Bは親会社と会計処理方法が一部異なっているが、気にしなくていいのか。
まず、(1)からです。
日本の会社ですと3月決算が圧倒的に多いですが、海外に目を向けますと12月決算が多く、そのため、在外子会社(海外にある子会社)も12月決算という会社が多いです。
こうした決算期のズレが親会社と子会社と間に存在するというケースがよくあります。
この場合、具体的に述べますと親会社の決算期が平成16年3月(平成15年4月~平成16年3月)で、子会社の決算期が平成15年12月(平成15年1月~平成15年12月)とします。
こうした決算期にズレがあった場合、合算するとしましたら平成15年4月~平成15年12月までは事業期間が一致します。しかし、1月~3月までの期間についてはズレが生じます。
そのため、平成16年1月に親会社と子会社とで取引を行った場合、連結財務諸表上は取引高の相殺消去を行わなければなりませんが、この取引は親会社の財務諸表(平成16年3月期)には計上されていますが、子会社の財務諸表(平成15年12月期)には計上されておらず、相殺消去する相手方がいないということになってしまいます。
それではこうした決算期の違いがあるとき、どのように考えればいいのか結論をいいますと、この取扱いは次の3通りになります。
イ)可能であれば、決算期間を統一する(連結財務諸表規則3条)。
ロ)決算期間を統一することが無理であれば親会社の決算期間にあわせて子会社は仮決算を行う。(連結財務諸表原則 第三 一般基準 二 連結決算日)
ハ)決算期間のズレが3ヶ月を超えないのであれば、子会社の財務諸表をそのまま合算し、重要な取引高についての調整を行う(同12条)。
上記のうち、実務上はハ)の方法を採用している会社が多いと思われます。
ただ、平成16年4月から四半期決算で連結ベースの財務状況の開示が要求されることを考えますと、3ヶ月のズレはかなりの影響を持ってきます。
そのため、イ)の決算期の統一を検討する会社が増えてくるかもしれません。
親会社と子会社は元来独立したそれぞれの会社であり、異なった経済環境で事業を行っていますので、会計処理方法に親子間で違いがあっても何らおかしくありません。
例えば、親会社と子会社とで製造している製品のライフサイクルが異なるというケースがあげられます。
すなわち、ライフサイクルが長い製品の評価基準は原価法を採用している。
一方、ライフサイクルが短い(例えばパソコンなど)製品については低価法を採用しているケースです。
こうした親会社と子会社との会計処理の原則及び手続は「同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、原則として統一しなければならない」とされています(連結財務諸表原則 第三 三 親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続)。
さらに、「同一環境下で行われた同一の性質の取引等」に該当するか否かの識別は、営業目的に直接関連する取引については、事業の種類別セグメント等ごとに判断します(親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い:監査委員会報告第56号)。
つまり、分かりやすくいいますと、損益計算書の営業利益より上に計上される項目にかかる取引(売上高、売上原価、販売費・一般管理費)については、同じ事業(例えばパソコンの製造)を行っているセグメント(事業単位)ごとに会計処理を統一するよう会計規定は求めているということです。
なお、固定資産の減価償却方法(定額法、定率法)については元々会社ごとではなく、事業所ごとに定めることができるとされていますので、連結財務諸表作成にあたって減価償却方法を統一することは要求していません(同委員会報告56号)。
また、上記以外に実務で問題となるのは連結子会社が税法基準で会計処理を行っているケースです。
ここでは簡単に述べるにとどめますが、退職給付引当金のように会計と税法との扱いがまったく乖離した場合、非上場会社が税法基準により退職給付引当金の処理を行っているとしますと、その金額に重要性が乏しい場合を除いて連結財務諸表作成上、修正が求められます。
こうした会計と税法の乖離、そして、その乖離を埋めるための会計処理である税効果会計についてもいずれ解説していきます。
ちなみに、税効果会計とは銀行決算で有名になりました繰延税金資産に係るものです。
